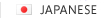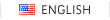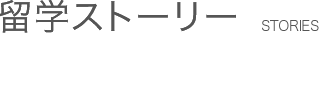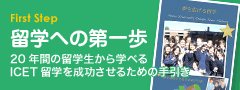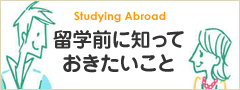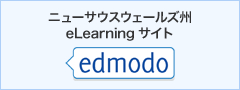保護者より
日本からのお便り
ICETの皆様そしてお世話になった皆様へ
3年間のオーストラリア留学!
私達とっては本当にあっという間の3年間でした。
中学卒業前の1月、14歳の長男をたった1人で私達も行ったことのないオーストラリアへ送り出す・・・。
見送りのホームでは言っておきたいことはたくさんあるのに、声をかけたら涙がとまらなくなるような気がして、新幹線に乗る間際に「身体に気を付けて。」 としか言う事ができませんでした。
ただただ、不安そうな顔をした息子を見送るのが精一杯で、胸をしめつけられるような感覚だったことを思い出します。
そんな息子の顔をみながらも、なぜか『きっとこの子は3年間泣き言も言わず立派にやりとげてくれるだろう・・・。』と、いう気持ちも少なからずも私達にはありました。しかし、息子を送り出してしばらくの間、毎日『本当に行かせてよかったのだろうか、まだ14歳の子供を1人で外国なんて・・・。』と、自問自答を繰り返し、息子からの連絡も無くこちらから掛ければ余計にホームシックになるかも?と、私達も精神的に苦しい日々が続きました。
今思えば、そうした経験のお陰で逆に私達が成長させられたと思い、感謝いたしております。
オーストラリアでの生活は語学だけではなく、今まで経験したことの無い、洗濯や食事、お弁当の用意などもして、自分のことは自分でする、という自立した生き方を学んだことでしょう。
ICETの先生方のサポートのおかげで、ホストファミリーに恵まれ、学校生活にも慣れていき、スポーツが大好きな息子は自分からサッカーチームや陸上クラブに入り、スポーツを通じていろいろな人達との交流を深めていくことができたと思います。
じっくりと息子を信じて見守って下さった先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。また、成績の面でも私達にわかりやすく面接時に説明くださり、安心させくださいました。(成績はといえば?…笑)
2年目、3年目はスポーツ、学校行事、ICETの行事に積極的に参加し日本の高校では出来ない体験をすることもできました。
はじめのうち周囲から「お金があるからできるんよな~」とか「よく行かせる気になったな~」とか、いろいろつまらないことを言われましたが、今、私達は心から3年間の留学をさせてよかった! お金などで買うことのできない貴重な3年間だったと胸を張って言えます。
見守って下さったICETの方々、デビットソンの先生方、そしてホストファミリーの皆様、本当にありがとうございました。感謝
そしてこれからも日本の子供たちが世界へチャレンジするチャンスを与え続けていただきたいと切に願っております。
我が息子が世界で活躍することが最大の恩返しと考えております。
そんな日を夢みて……
中家 圭一・富美代様よりいただいたメッセージです。
Fusae先生より
大変、嬉しいお便りをいただきました。
留学の成果に関しては、評価はいろいろに分かれます。それは、当たり前のことだろうと思います。人がみな違うように、体験もまた違います。
同じプログラムに参加したら同じような体験をしているように一見、見えますが、形は同じ体験であっても、そこから得るものは、一人ひとりみな違います。 授業も同じです。 先生の言葉は、それを聞き取る部分も、度合いも、解釈の仕方も、生徒一人ひとりによって違います。記憶となると、違いはさらに大きくなります。
留学に求めるものも生徒一人ひとり、保護者一人ひとりによって異なります。「成長」という言葉は頻繁に出てきますが、何を成長とするかはみな異なります。 「英語力」と一言で言っても、どこまで伸びたいか、どこまで伸びるかは、入り口のレベルによっても違うでしょうし、意欲によっても、また、努力の傾 注によっても違ってきます。 成果の出方も必ずしも数値で出るとは限りません。みな、それぞれに違うからです。
普段そういうことはあまり意識にのぼりませんから、留学の成果としてみな一様のものを求めがちです。しかしながら、成果もその評価もみな違うという ことを念頭に置きながら、次のお便りを読んでいただければ幸いです。
我が子の成長
先生、昨年1年間本当にお世話になりました。
とても嬉しい報告をさせていただけることを感謝します。
まず、英語力ですが、TOIECが去年の留学前は280点だったのが、先日は、720点でした。そればかりでなく、帰国して約3ヶ月弱になりますが、まだ一度も怒ることがありません。
また、留学前に比べて、妹を可愛がってくれるようになりましたし、私たちが何か一つしても「ありがとう」という感謝の言葉が口から出るようになりました。
勉強も頑張っているようです。明日からのテストに向けて、先週から、始発(5時2分)の電車で登校しています。6時過ぎに学校について、約2時間ほど 授業が始まる前に勉強
をしているようです。放課後も勉強し、うちに帰ってきても勉強しております。
そして、そんな中でも、ちゃんとお手伝いもしてくれています。
これほどまでに成長して帰って来てくれるとは、想像もしていませんでした。かけがえのない1年を過ごしてきたんだと、今の様子から実感しております。
これも、愛情をたっぷり注いでくれたホストファミリーと、それを見守りご指導してくださった、ふさえ先生をはじめとするICETの先生方のおかげだと思っています。
本当に心から感謝しています。ありがとうございました。
2010年8月 一生のうちの3年間を素敵なものに
昨年度留学生のお母様からのメッセージ
長男をオーストラリアの高校へ送り出してから1年半が過ぎようとしています。
中学校では勉強と部活動の陸上の練習に加え、小学校から続けていた剣道も引き続きやっていたので、かなり毎日が忙しかったのですが、主人の好きな音楽にも 興味があり、その合間にギターの練習などもやっていました。家族との海外旅行での経験や日本でも外国の方と触れ合う機会があったことから外国へ興味を持つ というバックグラウンドはありましたが、そんな生活の中、ふつふつと外国への関心(英語を学ぶということ)が深まってきたように思います。国語の作文にもその旨を記したり、私たちにも希望を話しだし、中2の終わり頃には留学の準備が始まりました。
主人も私もできれば子どもたちのやりたいことを優先にしてあげたい思いがありましたので、まずは、治安の良さ、学費などをもとに国や学校をたくさん調べました。
留学フェアが開催された時には東京にも繰り出し資料を集めました。数ヶ月をかけ調べた結果、オーストラリアの国に至ったわけですが、いろいろと調べていくうちにおばが住んでいる郊外の近くの高校にICETという留学システムがあることがわかり資料を送ってもらいました。
ICETの教育方針が言葉としての英語だけを学ぶものではなく、日本人としての英語教育のあり方を考え、将来的に国際社会に通用できるような教育を用意してくれているということに共感し、息子始め主人も私もここでなら得るものは大きいのではないかと決断しました。
新学期が1月からということで中3の1月23日(金)が出発日となりました。卒業式に出られないことが少し心残りでもありましたが、本人はそれでも留学への道を選択し、この日に出発しました。学年末試験の日でありましたので試験はしっかり受けてもらい、学らんを着たまま先生、友達に見送られ学校から成田へ直行しました。
長男が3年間家を空けるということをなかなか実感できないまま出発日が近づいて行きましたが、主人も二人の弟、妹も同じ思いであったようです。出発してから数ヶ月間はただ出かけているというような錯覚だけがあり、「あっ、彼はいないんだ」とたびたびみんなその言葉を口にしていました。そのうちなんとか慣れてはきたものの、いないことがしばらくの間本当に実感できず、長男の存在の大きさをそれぞれが改めて感じました。
中学校の方から3月までは在学中扱いになるとのことで担任の先生のご配慮もあり、毎週オーストラリアでの生活を記録したものを提出し、安心してもらいました。原田先生も息子の様子を随時メールにて連絡してくださったりと、日本とオーストラリアでの生活の移行も滞りなく進みました。
息子とのコミュニケーションはメールのみでしたが、毎日が新鮮で充実している様子で、大変なこともあったかとは思いますが、そんなことは感じさせないほど「楽しい」「楽しい」の連続の表現ばかりでした。それは今でも続いています。
学校の授業もたくさんのイベント(陸上大会、水泳大会、日本を紹介する日、ボランティアなどなど)もそれぞれに精一杯取り組めるような内容になっていることで、(失礼な表現ですが・・・)飽きることなく臨めているのかと思います。
1年目は英語の授業中心のようですが、日本の文化を学ぶ授業や国語もあり、現地の高校生と共に学べる授業もあり、と幅広く勉強することができることが魅力です。2年目は選択教科もかなり専門的になっているので、それらを学ぶ面白さもますます増え、宿題、課題は半端な量ではないかと思いますが、勉強のしがいがあり充実していると思います。タームごとに提出される成績表の評価の仕方も細かく分かれていて得意、不得意面もよくわかります。先生方のコメントもとても詳しく書かれているので学校生活を想像することができます。

オーストラリアという国で、自分はどんなもので、成果を将来にどう結び付けていきたいかなど、残りの1年半の学校生活、家での生活、旅行などの中でたくさん考えて、一生のうちの3年間を素敵なものにしてほしいと切に思っています。
遠い国とのやり取りもインターネットによって近くなったとはいえ、先生方のご配慮にはいつも感謝しております。勉強、生活とあらゆる面での先生方のフォ ローがあるからこそ子どもたちが元気にオーストラリアで伸び伸びと生活することができていると確信しています。貴重なこの時期にたくさんのご支援を本当に どうもありがとうございます。
10年後の子どもたちをぜひ期待してほしいと思っています。
2010年6月 「留学」とはひとえに「出逢い」
2009年 卒業生のお母様からのメッセージ

我が家の3人の子供のうち、長男と長女が「留学」という選択をしました。親から見たこの2人の軌跡を辿ってみたいと思います。
長男は語学関係の大学受験で悉く門徒を閉ざされ、第2の選択としてハワイトランスパシフィック校に留学しました。事前学習も準備もないまま、英語力も 最低レベル、見知らぬ土地で生活の仕方も勉強の仕方も分からず、 ほとんど何のサポートもないまま、何もかもひとつひとつ自分で切り開いていく形の留学でし た。同期入学で一番親しかった友達の僅か4ヵ月後の不慮の死、慣れない自炊生活での栄養失調、 期間内にクリアできなければ容赦なく退学させられる授業の厳しさ・・彼は助け合える仲間「コミュニティー」を作ることで乗り切っていきました。
そのことはサンフランシスコ大学 に編入する際、コミュニケーション学を専攻したことにも伺えます。このサンフランシスコ時代にも、 国籍も年代も様々な人たちと交流することで、彼の人生は 大きく変革していったように思います。同大学を今年5月に卒業するに当たり、夫婦で渡米しましたが、 あちらこちらで紹介される彼の人脈の多さには驚くと共に異国に根を張り、逞しく生きる我子の姿を目の当たりに見た思いでした。
一方、長女の場合は兄とは違い、留学への事前学習、準備期間もあり、またICETによる充分なサポート体制が整っていたため、生活のあれこれを心配する 必要がない分、 ひたすら自分の興味のあること、知識の探求に没頭していた3年間でした。初めて「本気」で取り組むものを見つけた彼女は、ICETが提供す る3年間の英語教育に加え、 更に、独自の勉強方で英語力を身につけ、「学ぶことの楽しさ」を体得し、確固たる自分を築き上げ、自信に満ちた人となりまし た。お世話になった三家庭のホストファミリー、 特に三軒目で一番長く滞在したCarapet家では「あゆみは4人目の我が家の子」と言っていただける程、 かわいがられ、パパであるOwen氏を心から尊敬し慕っていたようです。
しかしながら、この3年間における彼女の成長を、しかと受け止めることができたのは、ICETの存在を抜いては語ることができません。元々、多くを語らず、こちらが水を向けるとスルリとかわしてしまう傾向があった娘です。 彼女の頑張り、取り組み、生活の様子等は年次のレポートと共に、ICET校長である 原田房枝氏の報告によってもたらされたものです。 その親身で適切な報告と温かい励ましがなければ、私は彼女の成長の半分も正確に見ることはできなかったと思います。

娘との多くはないやりとりの中で、気にかかったことがあれば、精神面のことでも身体面のことでもICETのスタッフが即座に対応して下さいましたので、安心して娘を託すことができました。 今もって感謝の念に堪えません。そうして3年間をシドニーで過ごした娘は、「本当に自分の行きたい道、生きたい人生を選 べ」とのICETの指針を体現するかの如く、この7月からオーストラリア第2章 ラ・トローブ大学で環境学を学びます。
このように同じ「留学」でも2人のスタンスはかなり違います。共通して言えることは、圧倒的な経験の多さです。十代で親元を離れ、異文化の中でとまどいながら、悩みながら、日々積み重ねた‘勇気ある挑戦‘の連続です。 その挑戦の心こそが、自らの可能性を広げていったのです。最も私の垣間見た彼等の姿はご く一部であり、実際にはその何十倍もの経験や思いが横たわっているものと思います。 そしてそれは後方支援の親にとっても‘勇気ある挑戦‘であると同時 に、子供の成長という計り知れない喜びをもたらせてくれたものです。
日本は今、経済的にも社会的にも行き詰まりを見せています。多くの若者が生きつらさを感じながらも「ただ、何となく・・・」流されて生きています。
青年時代は人生の土台作りの時代です。人間としての器をつくる時代です。器を作るには厳しさも困難も忍耐も必要です。出来上がったものの中に保身と安住を 求めて生きるのか、 それとも新たな大地を耕し、種をまき、育てゆく創造的人生を送るのか、両者の誇りの高さ、充実の深さは比較にならないことでしょう。

「留学」とは ひとえに「出会い」ではないでしょうか。人との「出会い」自分との「出会い」人は人の中でしか成長できません。‘志が人をつくる大きな志は大きな人生をつくる‘と言います。その志との「出会い」。
ICETの教育は まさにその‘志‘を引き出し、育んでくれるものであったと思います。ICETに学んだ皆さんが志をもって世界に、社会に雄飛する姿をICETファミリーの一員として、私はこの日本で見守りたいと思います。
皆さんのご健康と活躍を心よりお祈り申し上げます。